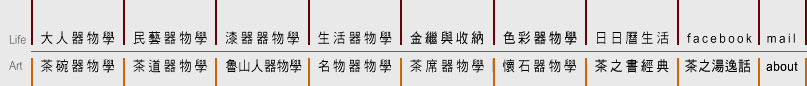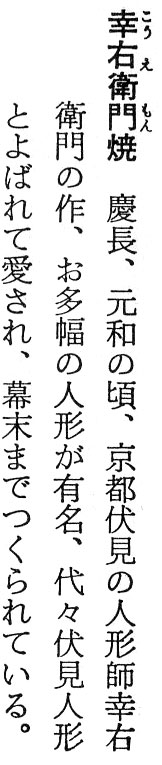日本的民藝陶- 京都府 幸右衛門焼 こうえもんやき
◇伏見人形の由来
天下に有名な伏見人形は 稲荷山の植土を以て造った最も古い郷土玩具であります。
全国で九十余種以上ある土人形のなかで、伏見人形の系統をひかないものはないといはれるほど我が国土人形の元祖であり、民俗的な美しさを誇っています。即ちその起源はむかしむかし土師部(はじべ・土でいろいろなものを造る人)は歴史に名高い野見宿称(ノミノスクネ)の後裔にあたる土師氏が統轄して土器を造っておりました。垂仁天皇の時代に朝廷より土師職に任命されまして、伏見深草の里に住んで土器、土偶(土人形)を創りだし茲に生まれたのが伏見人形であります。稲荷大社の祭事に使われる耳土器をはじめ、お使い姫の狐や饅頭喰いチョロケン、玉、でんぽ等、お馴染み深いものなど現在残っている原型、土型は三千種余り、往事の風俗、伝説を人形に表現したものが殆どで着想の飄逸、奇抜、ユーモアに富んだ面白さ、豊かな味、そしてその一つ一つににじみでている庶民的な素朴さは外国の人々にまで親しみをもたれています。
一休禅師の歌に 西行も牛もおやまも何もかも 土に化けたる伏見人形
(六代目丹嘉窯元 大西重太郎商店解説より)
唐人人形(朝鮮通信使)
幸右衛門は江戸時代末芝居「敵討天下茶屋」や講談でも扱われた人物らしい。「紀伊郡史」「伏見誌」「工芸志科」という明治大正期の書物でもそういう人物の存在が記されている。現在も相当数の幸右衛門名の入った人形が存在しているそうであり、偽物が相当作られたようである。作者名を入れた伏見人形は他に類例が少ないようで、その真偽をを疑う声は大きいようである。
私はつい最近「深草を語る」(深草を語る会編著・2013深草記念会発行))という本を頂いた。この本では「実在の人物であるかどうかは、すこぶる疑問である」としながら「幸右衛門は、この深草焼きの素焼きの土人形に泥絵具を塗って更に美しい人形を作り、人々を喜ばせていたのではないか」とどちらとも言えない書き方をしておられて、地元としては実在であってほしいということかなと読んだ。
伏見人形の中には「幸右衛門型」と呼ばれている布袋さんや眷属さんがあるようで、幸右衛門の名が江戸時代から明治・大正までビッグネームとして扱われたことは確かなようだ。