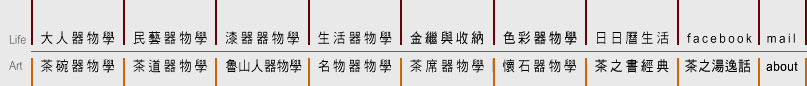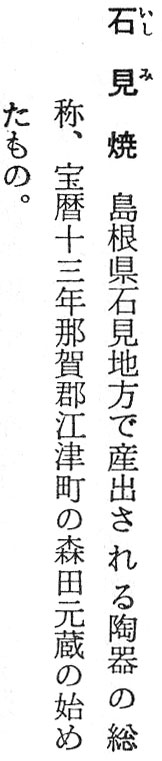日本的民藝陶- 島根県 石見焼 いしみやき
石見焼 いわみやき
中国地方、島根県の地域ブランド。
江津市・浜田市・大田市で製作されている。石見焼は、江戸時代中期から石見地方で焼かれている陶器の総称。特に、明治時代に量産された大はんどう(大水甕)は独特で、水道のなかった時代には水を貯蔵する生活用品として利用された。地元の都野津層の陶土を使い高温で焼成される。釉薬には来待釉や温泉津石などを使っているのが特徴。島根県ふるさと伝統工芸品。1994(平成6)年4月、通商産業大臣(現・経済産業大臣)によって国の伝統的工芸品に指定。
石見焼とは?
石見焼(いわみやき)は、島根県江津市周辺で作られている陶器です。
石見焼の特徴は、吸水性が低く強固で、塩分や酸・アルカリに強い素地(そじ)です。飯銅(はんどう)と称される大きな水甕(みずがめ)が有名で、そのほかにも茶器や食器などの小振りな生活用品が多く作られ、酸や塩に強いため、梅干しやらっきょう漬けなどの保存にも適しています。
石見焼には、磁器に近い地元で採れる良質の粘土が使われています。鉄分を含む深い茶褐色の「来待釉薬(きまちゆうやく)」が塗られた製品に加え、アルカリ成分を含んだ「温泉津石(ゆのついし)」を使った「透明釉薬(とうめいゆうやく)」の製品も主力となっています。透明釉薬を塗り、完全燃焼した炎で「酸化焼成(さんかしょうせい)」にて焼き上げると黄土色の製品が完成し、不完全燃焼の炎で「還元焼成(かんげんしょうせい)」にて焼き上げた場合には青色の製品が完成します。
History / 歴史
1592年(文禄元年)~1610年(慶長15年)の「文禄・慶長の役(ぶんろく・けいちょうのえき)」に出兵した武士が帰国する際に、朝鮮の陶工(とうこう)である「李郎子(りろうし)」を連れ帰り、現在の島根県浜田市や鹿足郡柿木村(かのあしぐんかきのきむら)で陶器を作らせたことが、石見焼(いわみやき)の始まりと言われています。
現在の島根県江津市において、1765年(明和2年)には本格的な製陶法が学び伝えられ、「片口(かたくち)」や「徳利(とくり)」などの小物陶器の製作技術は、周防国(すおうのくに)の岩国藩から招かれた陶工・入江六郎によって受け継がれました。水甕(みずがめ)などの大物陶器の製作技法は、1780年代(天明年間)に備前国(びぜんのくに)の陶工が島根県江津市に来訪し伝授したと伝えられています。
江戸時代末期になると、浜田藩の家老により、製陶業が殖産事業(しょくさんじぎょう)として奨励されたため、島根県江津市一帯は、水甕を中心とする陶器生産の一大拠点として発展を遂げました。